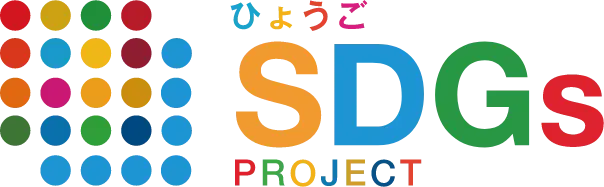公開講座「フェアトレード商品から始めるSDGs ~日々の買い物で世界に貢献~」
近畿大学産業理工学部経営ビジネス学科 坂田裕輔教授 FTマークを探すなど習慣化を
フェアトレード(FT、公平で公正な取引)とは、発展途上国で作られた農作物や製品を適正な価格で継続的に取引することにより、生産者の生活を支える貿易のあり方を指す。よく取り扱われる商品としてコーヒーやチョコレート、紅茶、砂糖、スパイスのほか、衣類、木・金属製品、陶器、革製品などがある。
FTの基準の一つが「最低価格の保証」だ。農作物の価格は天候や需要などで変動するが、持続可能な農業のために買い取り量や価格を事前に決めておく。また5年とか10年の「長期的な取引」が行われる。「有機農業の奨励」という基準もある。これは、農薬の規制が緩い途上国の生産者の健康被害を防ぐのが狙いだ。
もう一つが「強制的な労働の禁止」。労働基準がしっかりしていない国では、年間365日、1日14時間といった奴隷的な労働、子どもを働かせる児童労働も存在する。そういうことをしないようにというのがFTの趣旨だ。さらに「書面による労働契約書の作成」「民主的な運営」「男女対等の就労機会の提供」なども求められる。
FTは小規模農園とパートナーシップを組んで協力して行うものなので、大企業と大規模農園などの場合、FT認証を取らず、独自に取り組むケースも少なくない。それが持続不可能かというと、そうではなく、FTと非常に近い枠組みで行われている。
FTの商品は「高い」というイメージがある。僕は2024年9月に学生らと大水害を受けたタイ北部のチェンライを訪れ、支援のために現地の山岳民族からコーヒー豆を20キロ仕入れ、販売の準備をしている。普通の生豆は1キロ1500円ほどだが、4千円もかかった。うち1500円は送料だ。
FTコーヒーが高価な理由は、高品質である▽小ロットなので現地の手数料や送料が高い▽売れにくいから販売コストがかかる―などが挙げられる。では、売り上げが生産者にどれくらい渡るのかというと、コーヒー1杯500円として24円程度(約5%)と取り分は大きくない。
またコーヒーなどの農業生産のリスクとして病害虫や気候災害、生産者のけが・病気、世界的な相場の変動、取引先の業績悪化・倒産などがある。弱い立場にある生産者のリスクを供給事業者と消費者側がある程度カバーしようというのがFTの本質だ。
SDGsには17の目標があり、そのうちの12(つくる責任 つかう責任)が一番FTに近い。それでFT商品を買おうとしても、意志が弱かったり、忘れてしまったりして、なかなか始められないし、続かない。要は「頑張らないといけない」からだ。
行動するためには三つの壁があると言われている。一つ目は本当にやりたいと思う「関心・モチベーション」。次が手間や時間、お金、体力といった「面倒」。三つ目は分からないという「茫漠(ぼうばく)感」。どれくらいの苦労があるか評価できないと、人は動けない。
この壁をどう越えるかということを最近研究している。例えば、努力なしで行動を変えるこつとして、習慣化するというのがある。帰宅したらかばんをしまってうがいをするとか、FT商品にはマークが付いているので、スーパーに行ったらFTマークを探すというのもお薦めだ。
最後に楽しくやろうということ。日常生活をゲームにするというのも面白い。さまざまなFT商品のタイプをビンゴにして商品を見つけていったり、どこの店でFT商品が売っているのかをマップにして、自分の普段の行動範囲に組み込んだりすると、「面倒」の壁を越えていけるはずだ。